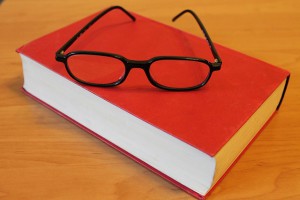久高島への山村留学について考えたこと -「不登校児再生の島」の物語-
「不登校児 再生の島」について、さらに書かせて頂きます。
この本は、子どもたち、センターのスタッフ、親御さんたちのもたらす物語こそが面白いのですが、物語の内容自体は「読んでみてのお楽しみ」ということで、そこは書きません。
ここでは、読んでみて私が感じた点を中心に書かせて頂きます。
「子供の問題行動は親へのメッセージ」という言葉があります。
子どもは、特に接する機会の多い母親から大きな影響を受けています。実際にこの本では、センターに子供を預けることで気づきを深める親御さんが多く登場します。
けれども、様々な事例を読むことで、問題の根っこは、当事者の子供・親御さんという家庭単位ではなく、親子関係を超えた現代のライフスタイル、社会のあり方まで含む、もっと大きなところから来る問題であるように思えます。
スマホ、ゲーム、テレビに代表される生活の身近に溢れかえる刺激的な娯楽。親は生計を支えるため外に出て働き、子どもは勉強・習い事などに忙しく親子間の会話もままならない生活。偏った、そして安全性に疑問の残る食生活。
このことは、多かれ少なかれ、ほとんど全員に当てはまるのではないでしょうか。むしろ、問題行動として露出している現象はほんの一部に過ぎず、多くの普通に生活をしている子供・親の場合でもたまたま今、何も起きていないだけで、今後何か起きる可能性は十分にあるように思えます。
そういった意味で、子供の問題行動については、単なる個々の問題と捉えず、大きな社会的な課題として捉えるべきではないでしょうか。
伝統的に優れていたシンプルで内面的なライフスタイルを、あまりにあっさりと破棄してしまい、何か(=お金、時間)に追い立てられるような、余裕のないバランスの悪い社会・ライフスタイル等を見直すことこそが大切だと感じます。
久高島という島内に幽閉(?)されたシンプルな規則正しいライフスタイルは、このような本質的な点を踏まえているからこそ、子どもたちのバランス、ひいては家族のバランスを取り戻すことが可能となっているのだと思います。
また、この物語を通じて、子どもたちは人間関係を創る経験が不足しているため、どのように人と人間関係を構築していったら良いかが分からない、という点もあるように思えました。
もちろん、私の子供時代でもそのような要素があったし、普通に学校生活を送っている子供達にも多かれ少なかれ、経験不足で接し方が分からない、ということがあると思います。
そんな中、センターや学校での横の関係はもちろんのこと、島の人々やスタッフとの縦の人間関係なども、健全さ、バランスの取れた社会生活を送るうえで、大きな役割を担っているように思います。
この本は、私が久高島、沖縄が好きだったから読み始めたという点はありますが、興味深く面白く、一気に読み進めました。
最後に、この本の子供たちの事例は、教育関係以外でも、発達心理学的にも興味深い内容だと思います。おすすめです。